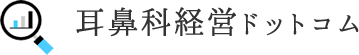消費者心理の変化
現代の医院マーケティングのあり方とは

クリニックの集患において、景気や季節の変動、競合の進出、天災などの外部環境の変化で集患が思うように進まないことが多々あると思います。
そのような時、先生方はどのような対策をお考えになりますか?
本記事では、今の時代の消費者行動心理から医院が取り組むべきマーケティングの考え方をご紹介します。
インターネットが普及し始め、情報通信端末の世帯保有率が2000年から増加傾向にあり、
2010年からはスマートフォンが台頭してきたと同時にスマートフォンの普及率が急速に増加しています。
今までは医療業界における新規患者(※)の来院経路は、
「口コミ・紹介」
が主軸となって構成されており、こちらを重視したマーケティングが主流でした。
※当記事では、新規患者とは『全く初めて医院に来院された患者さん』を指します。
しかしインターネットやスマートフォンの普及により、
新規患者の来院経路は「口コミ・紹介」と並んで「インターネット(WEB)」による来院動機が加わり、
主な来院動機の主軸が上記の2項目に変化してきました。
消費者の『情報共有』という行動
購買行動・購買心理の法則の一つとして、「AIDMA(アイドマ)の法則」をお聞きになったことがあるでしょう。
AIDMA(アイドマ)の法則とは、人が購買に至るまでどのような行動をとるかを示したものです。

さらに、近年のインターネットの普及が加速したことにより、電通が新たに「AISAS(アイサス)」というものを提唱しています。

AISAS(アイサス)の法則は、AIDMA(アイドマ)の法則に対して購買後に「共有する」というアクションがあります。
数年前であればツイッター、現在であればフェイスブックやインスタグラム、LINEというSNSの活用が良い例かと思います。
実際に自分が体験して良かったものに対しては、SNSを通して友人や他のつながりがある人に
「情報を共有する」
という行動をしているのです。
今は「地域名+診療科目」で上位検索表示されることが当たり前の時代に入っており、
その後の「Share(情報共有)」がより重要になっています。
今までの「○○耳鼻科は良かったよ~」という対面での口コミが、今後は場所・時間問わず発信されるのです。
医院の情報を共有してもらうには
「検索と共有」を患者さんにしていただくには、クリニックがそれらを行いやすいように誘導してあげなくてはなりません。
「Search(検索)」を強化するには、HPのブラッシュアップがあります。
自分が患者さんであれば
- どのような情報が欲しいか
- どのような検索方法を取るか
を考えて作り込む対策をとりましょう。
「Share(情報共有)」であれば、既存の患者さんが
- また行きたい
- 友人や家族に紹介したい
と思ってもらえるような取り組みをすることが、結果として「Share(情報共有)」につながります。
接遇や待ち時間対策、待合室の雰囲気や医院のコンセプトなどをしっかりと患者さん目線で行動心理を分析すれば、何が自院にとって必要な施策かがわかります。
先生お一人でアイデアが浮かばなければ、人員に余裕がある時や閑散期のスタッフさんにも手伝ってもらう、という手もあります。
消費者の購買行動心理の変化に合わせたマーケティングを行っていくことが、紹介や共有をしたいと思ってもらえる医院になる近道でもあるのです。
まずは自院の現状を再確認していただき、紹介や共有をしやすいマーケティング施策を講じていただければと思います。