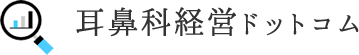耳鼻咽喉科医院における医師採用・雇用戦略のポイント
勤務医の採用、給与設計について

近年、物価高や労働市場の変化に伴う賃金引上げの必要性が高まり、人件費についてお悩みの先生方が多くいらっしゃることと存じます。
そして、人件費にはスタッフ(事務・看護師)だけでなく、院長先生以外の勤務医の方の雇用にかかるコストも含まれます。
そこで今回は、勤務医の給与設計や雇用体制の考え方について、医院のご状況を2パターンに分けてお伝えさせていただきます。
<1.既に勤務医を雇用されている医院様>
すでに勤務医を雇用されている耳鼻咽喉科医院様においては、このようなお悩みを抱えておられるのではないでしょうか。
「医療従事者の賃上げの波がある中、勤務医の給与をどうすべきか?」
一般的に、耳鼻咽喉科医の給与は他科目と比較して決して低くはありませんので、給与の調整を行う緊急性は低いと言えます。
ただし、複数名の医師を雇用している耳鼻咽喉科医院においては、状況が異なります。
その理由は、医師の診療スタイルやスキル等の差が生じやすくなるためです。
「処置も検査もしっかり実施する医師」
「処置検査が少なく、DO処方が多い医師」
「めまいの診療が得意な医師」
「手術ができる医師」
など、医師の診療スタイルやスキルが異なると、1時間あたりの診療報酬も変わってくるでしょう。
そうなると、医院経営に寄与する医師とそうでない医師にも分かれてきます。
そのような場合は、医師別に売上を集計できる仕組みを構築し、1時間あたりの売上が高い勤務医にはインセンティブを支給することをお勧めします。
1日の診療人数や月の売上が一定を超えた場合はインセンティブを支払うというような制度を設けておくことは、勤務医の方々のモチベーションに直結するためです。
また、仮に他院が賃金を上げて募集した際、優秀な勤務医が流出してしまうことを防止することにも繋がります。
次に、
「問題のある勤務医の雇用を維持すべきか?」
このような悩みをお持ちの先生もいらっしゃるのではないでしょうか。
例えば、
・1時間あたりに診療できる人数が少ない
・指導しても改善に前向きでない
・患者さんからの満足度が低い
といった理由から「この採用は失敗だったかも…」と思われるケースも一定数あるでしょう。
現在は医師を含む従業員の解雇は容易ではありませんので、経営状態の悪化以外での解雇は、明確な規律違反などがなければ困難です。
そこで、勤務医を解雇するのではなく、勤務態度における問題を改善していただく手段として、以下のような取り組みをご検討ください。
・連絡体制の見直し
・ドクターミーティング体制の構築
・医師専用の診療マニュアル の作成
・医師専用の接遇マニュアルの作成
これらの導入・整備によって「勤務医の指導フロー」を構築することが望ましいでしょう。
また、実際の運用においては、入職後に急な告知をするのではなく、入職前の採用面接などの場で、あらかじめ教育する項目や遵守してほしい内容について合意をとっておくことも重要です。
面接時に共感してくれた医師のみを雇用するための基準を設けるなど、採用時点からある程度フィルタリングする仕組みもご検討ください。
<2.勤務医の雇用を検討されている医院様>
勤務医の雇用を検討されている耳鼻咽喉科医院の多くは「1日あたりの患者数が多くなったため、自身の負担を減らしたい」という想いをお持ちのことでしょう。
それを踏まえて、雇用するのに適切なタイミングや条件についてお伝えさせていただきます。
■ 雇用するタイミング
結論から申し上げると、現時点で患者数が伸びている医院においては、院長先生の診療の負担を軽減するという観点から、積極的に雇用されることを推奨します。
具体的に申し上げると、患者さんの待ち時間や満足度、そして院長先生のご負担を考慮し、1日平均患者数が年間を通して120名を超えていれば、勤務医の雇用を検討して良いタイミングと言えます。
勤務医の雇用によって2診体制を作る場合、スペースやスタッフ人員の問題等が発生しますが、例えば、従来は休診にしていたコマで診療してもらう体制など、工夫次第で1診体制のまま経営を強化することも可能です。
ただし、医師の採用は難易度が高いです。
先生方もご存じの通り、「医師は採用市場で動いている絶対数が少ない」上に、数少ない面談に繋がったとしても「安心して任せられる医師に出会う」確率は決して高くはありません。
実際に、多くの先生方が勤務医の採用活動に踏み切りにくい理由の1つとして、「患者離れを引き起こすような医師を採用してしまうのではないか」というご心配もあることでしょう。
これまでに勤務医を雇用されたことがない医院様においては、採用や教育におけるご経験が不足している状況での採用には、失敗してしまうリスクも一定数あります。
そこで、リスクを最小限にするためにまずは常勤ではなく非常勤の医師を雇用することをお勧めします。
実際に勤務されるコマ数は週1コマからでも良いと考えます。
また、採用難易度という観点においても、少ないコマ数での勤務の方が条件に合う求職者が多く、 応募に繋がりやすいというメリットがあります。
さらに、まずは最小限の診療をお任せし、院長先生の診療の負担を少しずつ軽減してもらいながら、勤務医を教育するノウハウを蓄積していただくことも可能です。
その後、勤務医の採用・教育体制が整備された段階で常勤医師の雇用に踏み切ることが望ましいでしょう。
■ 雇用条件(目安賃金、時間)
耳鼻咽喉科は医師の絶対数が少ない中でも、2診体制や分院展開などに伴う医師のニーズが高く、他の科目と比較して賃金は高い傾向にあります。
もちろん、地域によって相場は変わりますし、スタッフの賃金相場と異なり、医師は「都市部が高く地方が低い」などとも一概には言えません。
そのため、全国的な賃金相場を調査・理解した上で、近隣エリアにある医院の募集賃金と比較し、自院の給与を設定いだくことが望ましいです。
なお、賃金は高ければ高いほど反響を見込むことができますが、収益とのバランスを考慮し
た適正金額で募集されることをお勧めします。
医師募集において反響を得るためには、高い賃金を提示する以外にも、働きやすさを訴求することも効果的です。
例えば、常勤医師においては「週3日勤務のプラン」「週4日勤務のプラン」といった勤務形態ごとの給与設定を行ったり、
常勤医師・非常勤医師に関わらず「標榜診療時間は18時半までのところ、17時までの勤務も可能にする」といった条件を設定されているケースもあります。
「標榜診療時間中は勤務すべき」という固定概念を捨て、勤務時間を短縮した雇用プランもご用意いただくことで、子育て中の女性医師など、より広い層からの応募を見込むことが可能です。
それでは、医師採用に関する解説は以上です。
勤務医の雇用は、耳鼻咽喉科医院経営の戦略において、極めて重要なポイントとなります。
採用や雇用中のマネジメントにおいてご不安のある先生は、弊社の無料経営相談もお気軽にご活用ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。