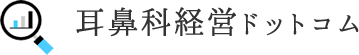クリニックにおける最低賃金引き上げに対する問題と対策
収益の改善による賃上げの原資の確保、無駄な経費の削減などによって対策を

2025年8月4日に発表された「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」では、過去最高となる63円の引き上げが目安とされました。全国の加重平均額は1,118円となっており、この63円の引き上げは1978年に目安制度が始まって以来、最高額となっています。
このような大幅な最低賃金の引き上げ、すなわち「賃上げ」は、医療機関を含む多くの業界にも大きな影響を与えるものです。
新しい最低賃金は、10月1日から11月1日までの間に順次適用される予定ですが、改定額や適用開始日は異議の申出状況等により変更される可能性があります。
本コラムでは、この「賃上げ(最低賃金引き上げ)」に伴いクリニックで生じる問題とその対策について解説いたします。
まずは、最低賃金の引き上げに伴う大きな4つの問題点について見ていきましょう。
1.人件費の増加
2.採用の難化
3.扶養内で働くスタッフのシフト調整
4.常勤スタッフのモチベーション低下
それぞれについて順に解説いたします。
1.人件費の増加
例えば時給50円の賃上げをする場合、フルパートスタッフ1名あたりでクリニックの負担は月で約7,000円増加することになります。
さらに人件費は法定福利費を含みますので、社会保険や労働保険などの法定福利費を考えるとさらに負担は増えてしまいます。
2.採用の難化
最低賃金が上がれば、採用コストも上がるのは当然です。
さらに昨年の最低賃金上昇のタイミングで時給を高く設定していても、周囲のクリニック・企業も一律に賃金を上げていけば時給の差別化が難しくなり、採用における競争力が低下してしまいます。
そうすると良い人材を採用するためにさらにコストをかけなければいけません。
3.扶養内で働くスタッフのシフト調整
扶養内で働くスタッフを雇用しているクリニックにおいては扶養範囲を超えないように労働時間を調整しなければなりません。
扶養内で働くスタッフが多いとシフトが組めなかったり、スタッフが休む場合に代わりがいなかったり、有給休暇を取ってもらうことができなかったりと様々な弊害が出る可能性があります。
4.常勤スタッフのモチベーション低下
パートスタッフのみ賃金を引上げて常勤スタッフの賃金を上げなかった場合、常勤スタッフにとっては不公平を感じてしまいます。
法律上仕方のないことですが、パートスタッフだけの賃金だけが上がると、頑張っている常勤スタッフからすれば自分の仕事が評価されていないように感じてしまうこともあります。
クリニック内のパートスタッフのベースがアップするのであれば、全スタッフが納得するような上げ方をしていただければと思います。
では最低賃金の引上げに対して指をくわえて見ていてはいけません。
それでは対策について4つ紹介します。
1.収益性の改善
2.スタッフのスキル向上
3.医療DXを活用した生産性向上
4.無駄な残業を減らす
1.収益性の改善
クリニックの経営安定のためには、単に医業収入を上げるだけでなく、経費を適切にコントロールすることが重要です。
ここでは、「収益性の改善」という視点から、売上拡大と経費削減の両面で検討できる具体的な施策を整理します。
<売上拡大策>
・処置・検査回数の見直し
新型コロナ禍以降、一度制限した処置をコロナ以前の水準まで戻せていないクリニックも多いのではないでしょうか。
例えば、ネブライザーの停止を見直して再開したり、ファイバーの使用基準をコロナ前の運用に戻すといった小さな取り組みが、年単位で見ると医業収入の底上げにつながります。
・患者数・レセプト枚数の改善
医院の強みを活かしたマーケティングの実施は当然ですが、診療時間が比較的短い舌下免疫療法やCPAP治療などから注力することで、オペレーション上の負担増を抑えつつ、患者数やレセプト枚数の増加を図ることができます。
・通院回数の見直し
通院回数は年々減少傾向が続いています。
特にコロナ前と比べて著しく減少しているクリニックは、運用の見直し余地があるかもしれません。
6歳未満の小児患者については、処置のための気軽な通院が、小児科との差別化となり、患者満足度向上に寄与する場合があります。
無駄な通院は避けつつも、患者の満足度を保ちながら必要回数を見直すことも検討ポイントです。
<経費削減策>
・人件費の最適化
業務フローの見直しや、タスクの再配分、パート・アルバイトの定期的なシフト調整により、人件費の適正化を図ります。
・医療材料・消耗品のコストコントロール
仕入先とは定期的に価格交渉を行うようにしてください。
・エネルギーコストの削減
設備稼働時間の最適化や、LED照明への切り替え、エアコンの適切な温度管理などにより、エネルギーコストの抑制をご検討ください。
・外注業務の見直し
清掃やメンテナンス業務など、一部外注業務の内容見直し・契約条件の再交渉といった、小さな積み重ねによる経費節減も重要です。
2.スタッフのスキル・生産性向上
人件費が上がりスタッフの仕事量が変わらなければ、生産性が低下していることになり、クリニックにとってマイナスでしかありません。
そのためスタッフにはまだできない仕事を習得してもらいましょう。
受付や介助スタッフが固定になっているクリニックは、受付なら電話・受付のみ、介助なら小児の押さえと洗い物のみでもいいので別のセクションの仕事ができる状態になることが第一歩です。
完璧を求めるとジョブローテーションは上手くいきません。
また、クラークを導入していない医院であれば、カルテをクラークに任せたり、介助スタッフの手が離せない場合にはクラークに診療補助を手伝ってもらえれば、1時間当たりの診療人数が増え、生産性が上がることになります。
まずは2~3人から上手くジョブローテーションを使って仕事の幅を広げてもらうようしましょう。
もしスタッフの反発が怖くて新しい仕事をしてもらいたいのになかなかスタッフに言い出せない先生がおられましたら賃金改定を機にスタッフに伝えるきっかけにしてもらえればと思います。
3.医療DXを活用した生産性向上
現在、人手不足でスタッフ募集を検討している医院においてはスタッフ採用と別軸で医療DXで対応できないかもご検討ください。
例えばレセプト業務においてスタッフの教育コスト、残業時間を削減できるのであればレセプトチェッカーの導入を検討してもよいかと考えます。
レセプト業務は新人スタッフにすぐ教えることが難しく、対応できるスタッフが限られてしまうなど、引継ぎが困難な業務の一つです。
そのため、医療DXの活用による業務の効率化・標準化を検討することもお勧めです。
医療DXを導入する際の判断基準としては、削減できる労働(残業)時間にスタッフの時給を掛けたコスト削減効果が、導入システムの時間あたりのコストを上回る場合には、導入を前向きに検討しても良いのではないでしょうか。
4.無駄な残業を減らす
必要な残業と不要な残業を見極める必要があります。
慣例的に朝は30~45分前に来て準備をすることになっているが、それがいわゆる朝残業となっているという医院があります。
・朝の準備は本当にその時間必要なのか?
・本当に全員がその時間に出勤する必要があるのか?
・その準備の一部は前日に行っておけない内容なのか?
など、見直しを行うことで時間か人数の削減ができる可能性があります。
午後の診療後においてもレジのお金を一人が数えて、他のスタッフはそれを何となく待っている。そして全員同じ時間に退勤を押している医院もあります。
診療受付が終わっているのに、受付にいて診療終了後に掃除をしている。
etc.
医院にはこのような慣例行事になっている仕事があったり、隙間時間を上手く使えていないスタッフがいたりと、無駄な労働(残業)時間がいくつかあるはずです。
最低賃金が引上げられることが決まり、収益の改善による賃上げの原資の確保とスタッフの雇用問題に対策できると同時に無駄な経費の削減などによって対策を打っていかなければなりません。
私たち株式会社クレドメディカルは、医療機関に特化したコンサルティング会社として、開業後の継続的な発展と安定した経営をサポートしています。
今回のような最低賃金引き上げに伴う賃上げへの対策の他、花粉症シーズンの乗り切り方や、診療報酬に関する重要なお知らせなども随時お届けしております。是非メールマガジンのご登録をお願いいたします。
また、最低賃金の引き上げに伴う賃金設計から経営数値・処置検査回数の見直しまで、幅広いご支援を承っておりますので、ご質問やご依頼がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
本コラムが、耳鼻咽喉科医院の経営に少しでもお役立ていただけましたら幸いです。